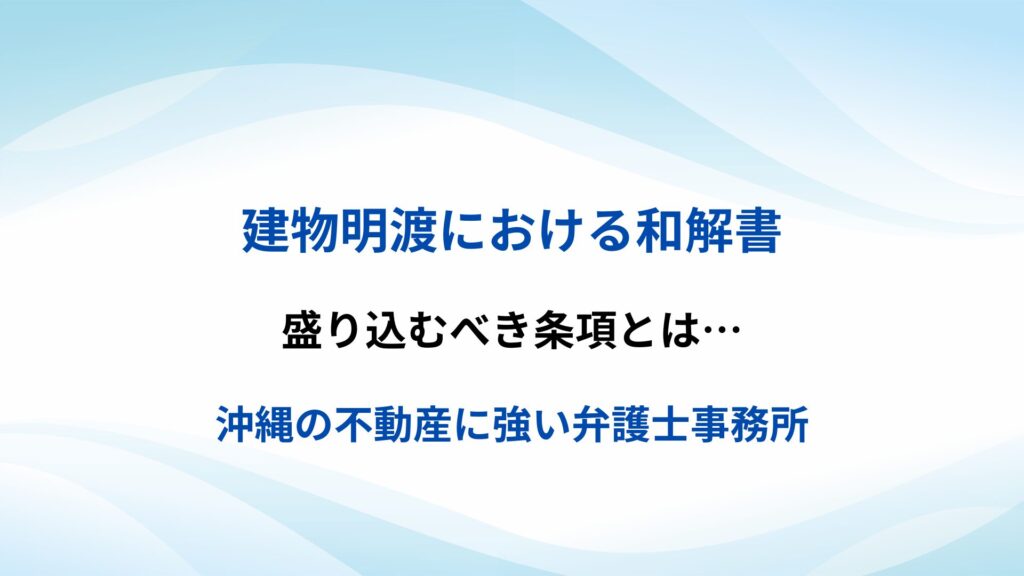任意退去交渉時の注意点
家賃が2カ月滞納されている状況で、賃借人と連絡が取れる場合は、「命令」ではなく「提案」の形で任意退去と滞納家賃の支払いを促しましょう。
例えば、「賃借人様の収入状況では、現在の家賃は少し負担が大きいかもしれません。このまま住み続けると、さらに滞納が増えてしまい、生活がより厳しくなることが懸念されます。より手頃な家賃の物件に引っ越されることで、今後の生活を再建し、安定させることができるかもしれません」といった内容で話を進めると良いでしょう。ここでのポイントは、賃借人に対し協力的な姿勢を見せることです。
このようなアプローチにより、賃借人が任意退去に応じる可能性が高まります。ただし、注意すべき点として、安易に滞納家賃の分割払いに関する合意書を交わすことは避けましょう。仮に合意書を作成しても、それに法的な強制力を持たせるには別途訴訟が必要ですし、滞納している賃借人の多くは一時的な対応として支払いの意思を示すことが多いため、実際に支払われる保証はありません。2カ月分の家賃が支払われなければ、賃貸契約は正常化しないという点を強調し続けることが重要です。
強制退去に向けた法的手続きの準備
任意退去と一部家賃の支払いを交渉する一方で、「強制退去に向けた法的手続き」の準備も進めましょう。具体的には、滞納家賃が3カ月分に達した段階で、すぐに「建物明渡訴訟」を起こせるように備えておく必要があります。この準備には、自分で訴訟を提起するのか、弁護士に依頼するのか、また依頼する場合はどの弁護士に頼むのか、さらにその費用についても事前に検討しておくことが含まれます。
弁護士に依頼する場合は、コストを抑えつつ迅速に対応してくれる弁護士を事前に選定し、必要な場合にはすぐに依頼できる状態にしておくことが理想です。裁判では、家賃滞納が3カ月以上になると、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたとみなされ、賃貸借契約の解除が認められる傾向があります。これを「信頼関係破壊の法理」と呼びます。
滞納が3カ月に達してから弁護士を探し始めると、手続きに1カ月以上かかり、その間にも家賃の損失が発生してしまいます。したがって、家賃滞納が2カ月分に達した時点で、弁護士を選定し、可能であれば事前に打ち合わせを完了させておくことが、最善の準備となります。
ロゴver3.png)


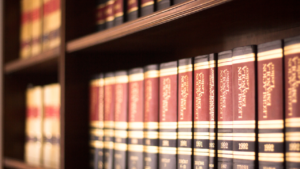


.jpg)