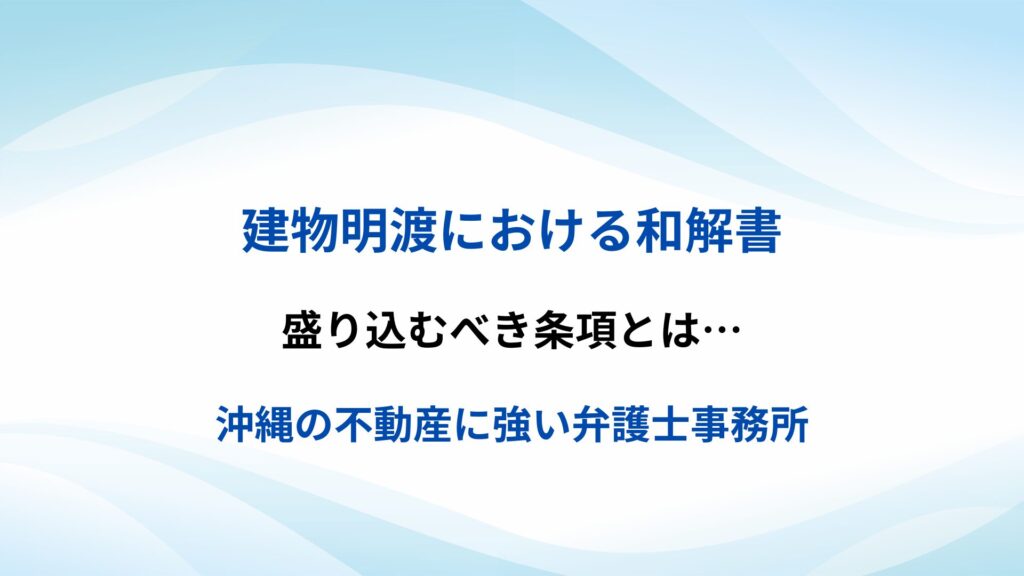家賃を増額することは、以下の条件を満たせば可能です。ポイントは、賃借人との合意、法律上の要件、そして経済的な状況に応じた対応です。以下、具体的な条件や手続きについて説明します。
1. 賃料増額の基本的な考え方
1-1. 当事者間の合意による賃料変更
賃貸借契約は、賃貸人(オーナー)と賃借人(入居者)の間で締結される契約であり、双方の合意によって内容を変更することが可能です。このため、賃料も合意があれば、増額することが可能です。
- 合意の方法
- 賃料を増額したい場合、まずは賃借人と話し合いを行い、合意を得ることが理想です。賃料改定の理由や背景を説明し、双方が納得した上で契約の修正を行います。
1-2. 合意が得られない場合の増額請求
もし賃借人が賃料の増額を拒否した場合でも、借地借家法に基づいて、一定の条件が満たされれば、賃貸人は賃料増額請求を行うことができます。特に、以下のような事情があれば、賃借人の同意がなくても、法的に賃料を引き上げることが認められます。
2. 賃料増額請求ができる条件
2-1. 借地借家法に基づく増額請求の条件
借地借家法第32条(建物の賃貸借における規定)や第11条(土地の賃貸借における規定)に基づき、以下の条件の下で賃料増額を請求できます。
① 租税その他の負担の増減
例えば、固定資産税やその他の税金が上がった場合、オーナーにかかる経費が増加するため、賃料を見直すことが正当な理由となります。
② 経済事情の変動
土地や建物の価格が上昇した場合や、物価上昇などの経済環境の変化があれば、賃料が不相当になることがあります。このような経済事情の変化も賃料増額の理由になります。
③ 近隣物件の賃料との比較
同じエリア内で、類似の物件の賃料と比べて現在の賃料が低すぎる場合、オーナーはそれを根拠に賃料増額を請求できます。
2-2. 賃料増額の交渉が不調に終わった場合の対応
もし、賃借人が増額に合意しない場合、賃貸人は調停や訴訟などの法的手段を取ることが可能です。しかし、賃借人が増額に合意しない状況では、裁判所に判断を委ねることになり、最終的に増額が認められるかはケースバイケースとなります。
3. 賃料の「継続賃料」とは
3-1. 継続賃料の算定
賃料が不相当であるかを判断する際、継続賃料の算定が重要です。これは、賃貸借契約が継続する場合の適正な賃料を意味し、物件を新規に募集する際の賃料(新規賃料)とは異なります。継続賃料は、現在の賃料や経済状況を踏まえ、増額または減額されるべきかが判断されます。
3-2. 不動産鑑定の必要性
賃料が不相当かどうかの判断には、不動産鑑定士による鑑定が有効です。ただし、鑑定には通常30万~50万円程度の費用がかかるため、増額分や賃借人との交渉の見込みを考慮し、慎重に対応する必要があります。
ロゴver3.png)



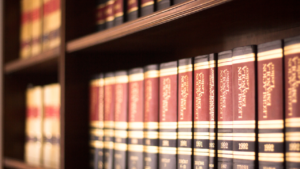


.jpg)