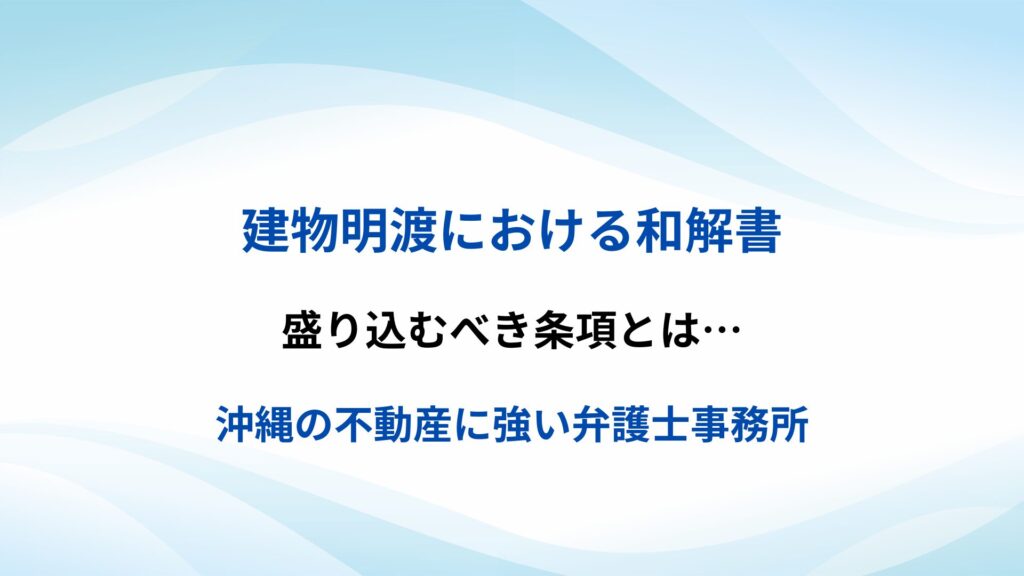弁護士が監修する
「賃貸契約見直しプラン」
契約内容に不安を感じていませんか?
専門の弁護士が、オーナー様の利益を最優先に考えた契約見直しをサポートします。
「契約書のレビュー」
「契約内容の改善提案」
「トラブル回避策」の提供
「専門家との連携」
お気軽にお問い合わせください。
契約の一部を修正したり、補充したりする際には、覚書(または合意書)を締結することで、変更内容を正式に記録することが一般的です。この覚書は、元の契約と一体として機能し、元契約を補足・修正する役割を果たします。
覚書はどのような場面で有効になるか?
- 価格変更をするとき:取引商品の価格や賃料の増減額を行う場合
- 納期の変更の変更をするとき:商品の納期や引渡し時期を延長または短縮する場合
- 支払い条件の変更をするとき:支払期日や分割払い条件を修正する場合
- 役務提供内容の修正をするとき:契約内容に変更や追加の役務が発生した場合
覚書を締結することで、契約の一部変更が正式に記録され、双方にとって法的に有効な形となります。重要なポイントは、元契約の条項を考慮した上で、覚書の内容を詳細かつ明確にすることです。
覚書を締結する際の基本的なポイント
原契約の特定する
覚書が元の契約を修正・補充するためには、まずその原契約を特定する必要があります。契約書名、締結日、契約当事者の名前などを正確に記載し、覚書がどの契約に対するものであるかを明確にします。
◆例
「2024年9月1日付で締結された賃貸借契約(以下「原契約」といいます)について、以下の通り内容を変更する。」
変更内容を明確にする
覚書では、変更する具体的な条項や内容を明確に記載します。例えば、代金の増減額、納期の変更、取引条件の見直しなど、変更する部分を正確に表現します。また、新たな条項を追加する場合も、覚書にてその旨を明記する必要があります。
◆例
「原契約第5条に定める賃料を、2024年10月1日以降は月額○○円に改定する。」
変更時期の記載する
変更がいつから有効となるのか、具体的な日付や時期を明示します。これにより、変更がどの時点から適用されるか、両当事者の間で明確に合意されます。
◆例
「本覚書に基づく変更は、2024年10月1日より効力を有するものとする。」
元の契約との一貫性を強調する
覚書が元の契約と一体として機能することを明示し、元契約のその他の条項は引き続き有効であることを確認する条項を加えるのが一般的です。
◆例
「本覚書に定める変更を除き、原契約のその他の条項は、引き続き有効に存続するものとする。」
署名・捺印
契約の修正に関する覚書も、元の契約と同様に、当事者の署名または捺印が必要です。両当事者が変更に同意したことを示すため、正確な署名・捺印が求められます。
自分で行うことのリスク
1. 契約書の曖昧な表現による誤解
契約の修正や覚書を自分で作成する場合、法的に正確な表現や条項を使わないと、契約内容が曖昧になり、誤解を招くことがあります。この結果、双方が異なる解釈をする可能性があり、後々のトラブルに発展するリスクがあります。
- 例:代金変更の条項が不明確だと、相手側が異なる金額や条件を主張する可能性がある。
2. 法的効力の欠如
契約変更や覚書に関する法律的な知識が不足している場合、法的に無効な契約書を作成してしまうリスクがあります。契約内容が法律に違反していたり、必要な要件を満たしていないと、後にその契約書が法廷で無効とされる可能性があります。
- 例:契約変更の際に必要な法的要件(例えば、適切な署名や捺印、適法な条項の記載)が満たされていない。
3. 不公平な契約内容の採用
自分で契約の修正を行うと、知らないうちに不公平な契約内容を相手に提示してしまうことがあり、後からその点を指摘される可能性があります。相手側が不利な条件を押し付けられたと感じた場合、契約が無効とされるか、法的な争いに発展するリスクもあります。
- 例:支払条件の変更で一方的に有利な条件を導入した場合、相手がそれを不服とする可能性がある。
4. 原契約の影響を軽視するリスク
契約変更を行う際に、元の契約内容との整合性を軽視することで、後に元契約との齟齬が生じるリスクがあります。覚書が元の契約内容と矛盾してしまったり、一体として機能しない場合、双方が混乱し、法的に不利な立場に立たされることがあります。
- 例:元契約で定めた納期と覚書の納期が一致していない場合、どちらの契約が有効か不明確になる。
5. 税務や法的責任の見落とし
契約内容の変更が、税務面や法的責任に影響を及ぼす場合があります。例えば、契約金額や取引条件の変更が税金にどのように影響するかを理解していないと、後に追加の税金が発生したり、予期しない費用負担が生じるリスクがあります。
- 例:代金の増額により、消費税や所得税の申告が適切に行われず、税務署から指摘を受ける。
6. 相手方とのトラブルや信頼関係の悪化
契約の修正を一方的に進めることで、相手方との信頼関係が損なわれるリスクがあります。覚書の内容に相手が納得しない場合や、交渉過程で十分な合意が得られなかった場合、ビジネス上の関係が悪化することもあります。
- 例:取引条件の変更を強引に進めた結果、相手方が取引を拒否したり、訴訟を提起されるリスク。
7. 法的紛争のリスク
自分で契約を変更した際、内容が不適切である場合には、後々法的紛争に発展するリスクが高まります。相手方が契約の有効性や条項の解釈を巡って異議を申し立てた場合、法的手段を通じて解決しなければならなくなり、時間と費用がかかる可能性があります。
- 例:代金の支払い方法についての変更が不明確で、相手が支払いを拒否することで訴訟に発展する。
ロゴver3.png)


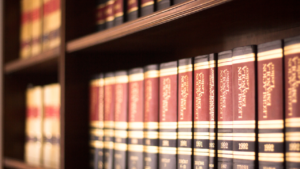


.jpg)