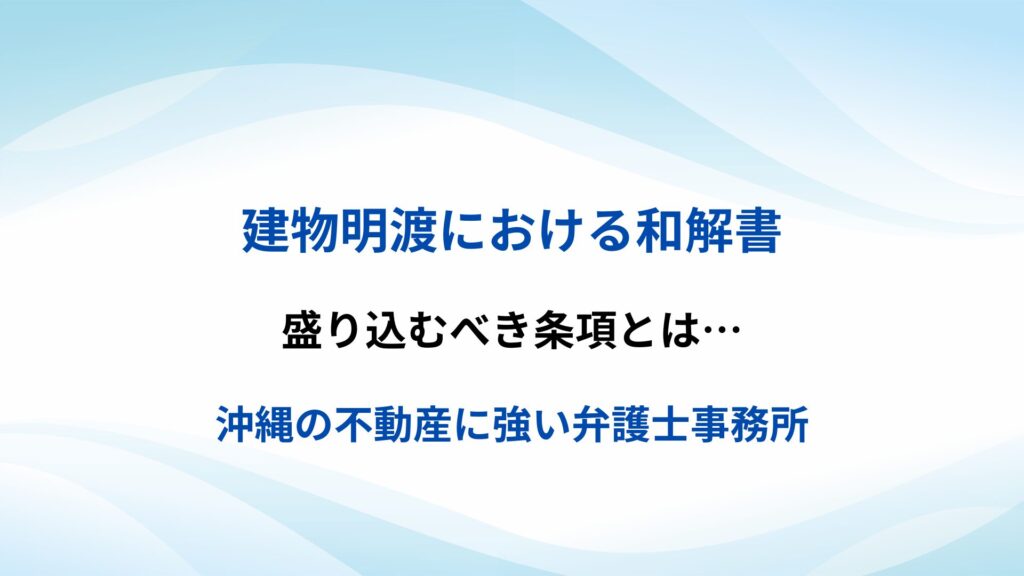スムーズな解決を目指す
「原状回復サポートプラン」
原状回復についてのトラブルでお困りですか?
法律の専門家が、適切なアドバイスでオーナー様を支えます。
「原状回復の基準」解説
「トラブルの解決支援」
「専門家による見積もり」の提供
「法的手続き」のサポート
お気軽にお問い合わせください。
賃貸借契約の終了後に借主が物件を明渡す際、借主には原状回復義務が発生します。しかし、この原状回復義務は、物件を借りた当初の状態に完全に戻すことを意味するわけではありません。通常の使用による経年劣化については、借主が負担する必要はなく、主に故意または過失による損傷や汚損の修繕が求められます。
この原状回復の範囲に関しては、敷金の返還時にトラブルが発生しやすいポイントです。借主とオーナーの双方が原状回復の範囲を巡って意見が対立することが多く、こうした場合、弁護士が代理人として交渉を行うことがあります。また、交渉で解決できない場合は、民事調停や訴訟に発展し、法的手続きによって解決を図ることも一般的です。
さらに、賃貸借契約が終了したにもかかわらず、借主が物件を明け渡さないケースもあります。この場合、契約はすでに終了しているため、借主に対して家賃を請求することはできませんが、賃料相当損害金という形で、家賃に相当する金額の損害賠償を請求することが可能です。オーナーはこの損害金を基に、借主から賠償を受けることができます。
原状回復の範囲は?
原状回復の範囲については、賃貸借契約において非常に重要なポイントであり、契約終了時のトラブルを回避するためにも明確に理解しておく必要があります。以下のように、借主が負担するべき損傷や修繕の範囲と、負担しなくてよい範囲に分けられます。
1. 借主が負担する必要のある原状回復の範囲
これらは通常、借主の過失や故意、または通常の使用を超えた損耗・損傷に該当するものです。
- タバコのヤニや臭い
借主が喫煙していた場合、そのヤニや臭いによる壁紙や天井の汚損は、通常の使用を超えるものとして修繕費が借主負担になります。 - ペットによる損傷
ペットが部屋を傷つけた場合(床や壁の引っかき傷や臭いなど)、借主に修繕義務があります。 - 釘やネジでつけた穴や破損
借主が壁に釘やネジを打ちつけてできた穴や、それによる損傷は、通常の使用を超えるため、借主の負担で修繕する必要があります。 - 飲食によるシミやカビの発生
借主の不注意でこぼした飲食物によるシミや、通風不良や清掃不足によって発生したカビなどは、借主の管理責任とみなされます。 - 子供の落書きや傷
子供が壁や床に描いた落書きや、遊びによってできた傷も、借主が修繕すべき損傷の一例です。 - 家具の移動や使用による床のへこみや傷
重たい家具を設置していたことで床に生じたへこみや、移動時に生じた傷なども借主負担での修繕対象となります。
2. 借主が負担しなくてよい範囲(経年劣化)
これらは、時間の経過や通常の使用による劣化として扱われ、借主の負担にはなりません。
- 壁紙の自然な色あせや剥がれ
日光による壁紙の変色や、接着剤の劣化による自然な剥がれは、経年劣化とみなされます。 - 床や畳の擦れや色あせ
普通に生活していれば生じる床や畳の擦れ、色あせなどは、通常使用によるものであり、借主は修繕費を負担しません。 - 設備の劣化による損耗
給湯器やエアコンなど、長期間使用して生じる劣化や故障は、オーナーが修繕や交換する責任を負います。 - 画鋲程度の小さな穴
壁に画鋲や小さなピンを刺した場合、その程度の穴は通常使用の範囲内とされ、修繕費を請求されることは一般的にありません。
原状回復を相手側が容認しない場合は?
借主が賃貸物件を退去する際に原状回復義務を果たさない場合、オーナーとしては次のステップを踏むことが考えられます。これにより、トラブルを適切に対処し、必要な費用を回収することが可能です。
1. まずは書面で通知する
最初のステップとして、借主に対して書面で原状回復義務を果たしていないことを通知します。この通知には、具体的な修繕内容や原状回復の必要性を記載し、修繕の履行を求める期限を明示します。丁寧な文章で対応を求めることで、話し合いによって解決できる場合もあります。
2. 敷金から修繕費を差し引く
もし借主が敷金を預けている場合、オーナーは原状回復にかかる修繕費を敷金から差し引くことができます。ただし、その際には修繕費用の内訳や金額を明示し、残金があれば返還する必要があります。また、修繕費が敷金を上回る場合、差額を請求することも可能です。
3. 第三者による見積もりを依頼する
もし修繕費の見積もりについて借主が異議を唱えた場合、第三者の専門業者による見積もりを依頼することが有効です。公正な見積もりを基にして借主と再度交渉を行うことで、納得を得やすくなります。
4. 弁護士による交渉
借主が交渉に応じず、原状回復をしない場合、弁護士を介して代理交渉を行うことが次のステップです。法律の専門家が介入することで、借主に対して法的な責任を認識させ、合意に至る可能性が高まります。
5. 民事調停を申請する
交渉が決裂し、借主が原状回復義務を果たさない場合は、民事調停を申請することができます。調停委員が仲介し、双方の意見を調整しながら解決を図るプロセスです。これにより、訴訟に進む前に円満な解決を目指せます。
6. 訴訟を提起する
もし調停でも解決が難しい場合、最終手段として訴訟を提起することが考えられます。裁判所を通じて法的に原状回復費用を請求する手続きです。訴訟は時間と費用がかかるため、事前に弁護士に相談し、費用対効果を確認してから進めることが重要です。
7. 賃料相当損害金の請求
また、借主が物件の明け渡しをしない場合、すでに賃貸借契約が終了しているため家賃を請求することはできませんが、賃料相当損害金として家賃相当額の損害賠償を請求することができます。これは物件を明け渡さないことでオーナーが被った損害に対する補償です。
ロゴver3.png)


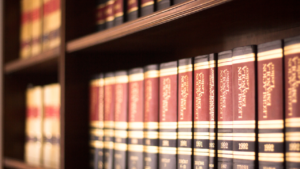


.jpg)