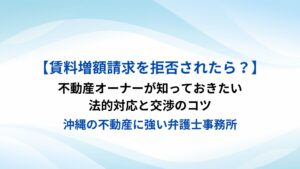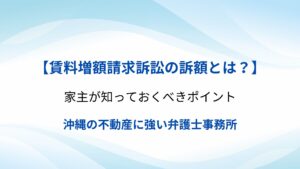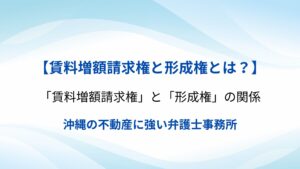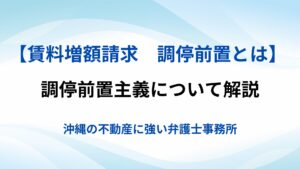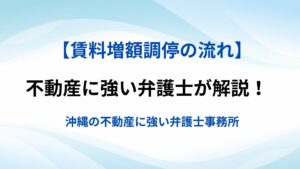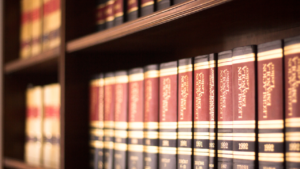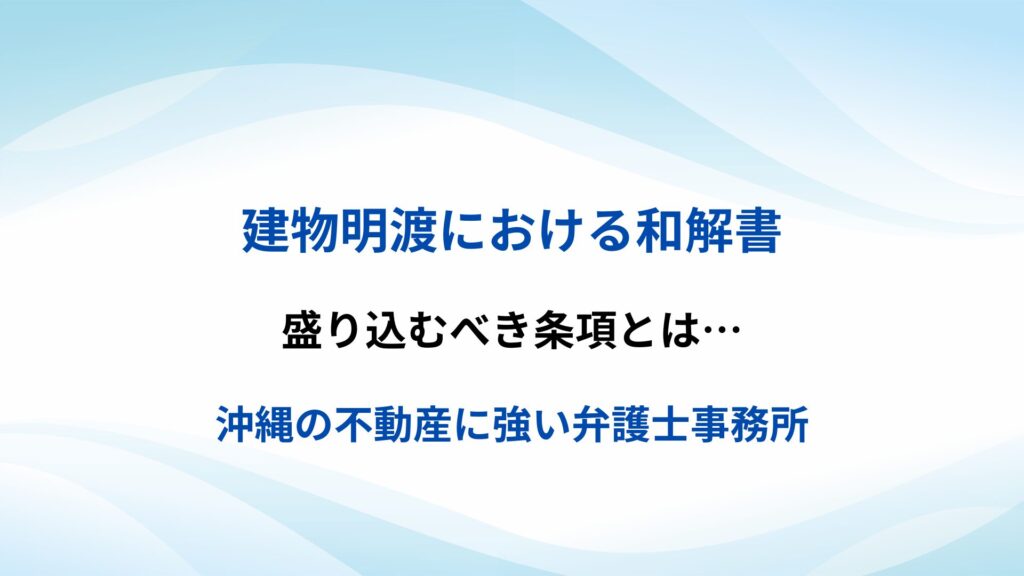賃料増額請求は、現行の賃料が不相当であると認められた場合に行うことができます。賃料が不相当かどうかは、借地借家法第32条第1項に基づき、いくつかの判断要素を総合的に考慮して判断されます。この記事では、賃料増額請求が認められる要件について、わかりやすく解説します。
目次
賃料増額請求が認められる主な要件
- 土地や建物に対する負担の増加
土地や建物に関連する公租公課、地代、公共料金の増額などが理由で賃料が不相当になることがあります。これらの負担増加が賃料増額請求の根拠となる場合があります。 - 土地や建物の価格上昇や経済状況の変動
土地や建物の時価の変動、物価や国民所得の変動など、経済状況の変化も賃料増額の要因として考慮されます。これにより、現行賃料が適正な水準を超えていると判断される場合があります。 - 近隣同種建物との賃料比較
賃貸物件と同様の用途や規模を持つ近隣物件の賃料と比較して、現行賃料が低すぎる場合、増額請求が認められることがあります。同じ建物内であれば、階数や位置などを考慮して比較されます。
不相当性の判断基準とその他の要素
賃料が不相当かどうかを判断する際、上記の要素に加え、賃貸人と賃借人の関係性や契約締結時の事情なども考慮されます。例えば、契約当初は良好な関係があり賃料が低めに設定されたものの、その後関係が悪化した場合なども判断材料となり得ます。
適正賃料と増額請求の制限
賃料増額請求は、賃貸人が一方的に行使できる権利ですが、増額できる額には制限があります。それは「適正賃料」に基づくもので、適正賃料を算出するためには不動産鑑定士による鑑定が必要です。適正賃料を裁判所が自ら算出することは少なく、専門家である不動産鑑定士が選任されることが多いです。
おわりに
賃料増額請求を行うには、現行賃料が不相当であると認められる必要があります。増額請求の要件を満たすためには、法的な判断が絡むことが多いため、不動産に強い弁護士のサポートを受けることが重要です。もし賃料増額請求に関する問題でお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ロゴver3.png)
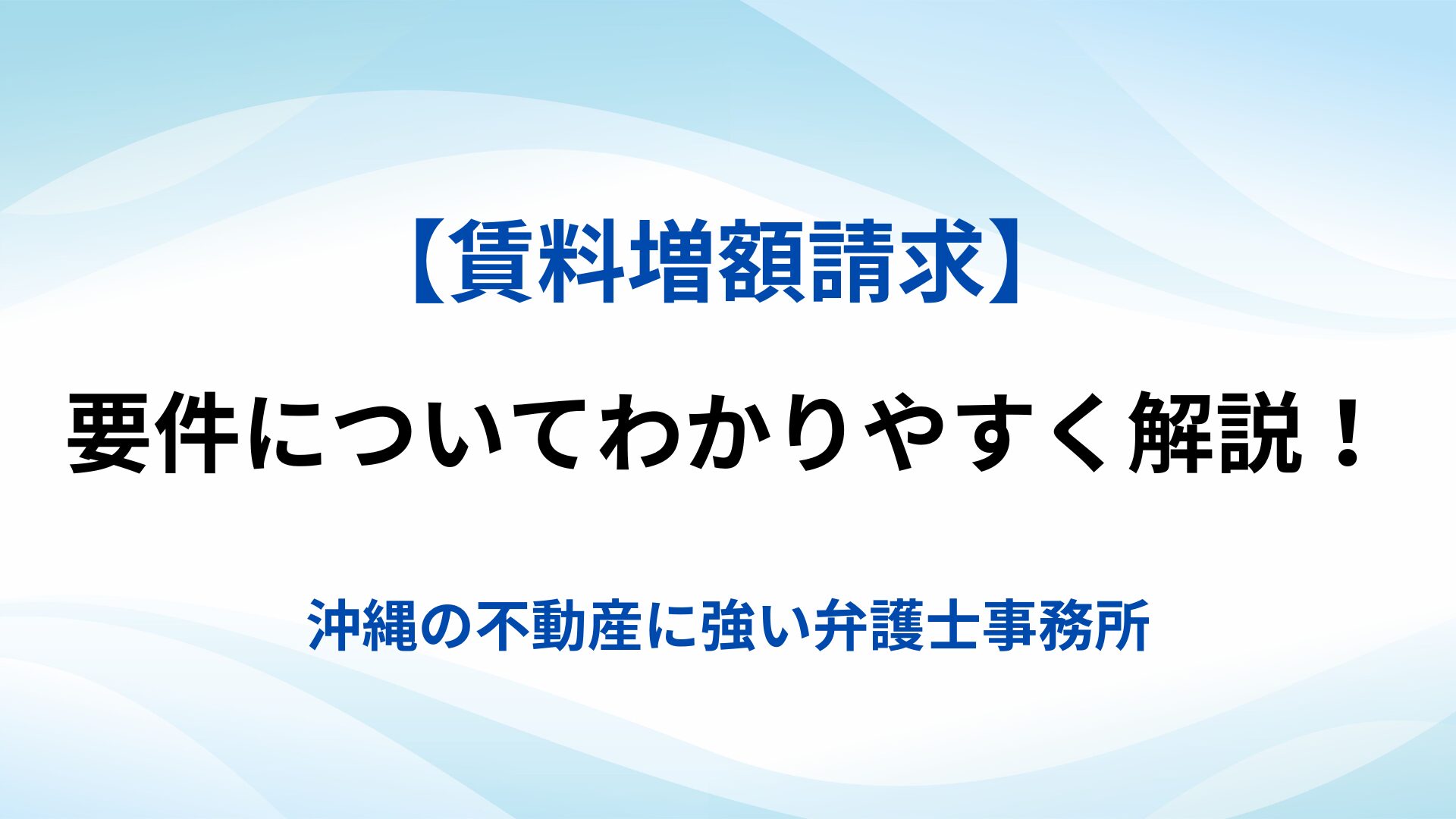
.jpg)